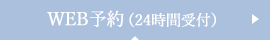先日、小麦アレルギーの患者さんを診察していた時のことです。
「これまでは小麦を食べちゃいけないと思ってずっと制限していたんですが、先生の動画を見て、小麦が原因ではないということを知って、食べ始めてみたんです。すると、またアレルギー症状が出て来てしまって」
というお話でした。
私は、これまで小麦アレルギーなどの食物アレルギーは、食物自体が原因ではないという主張をして来ました。そして、その根本的原因である腸内環境を整えれば、食べることができるようになるという内容の動画も発信して来ました。
最近では、遅延型食物アレルギーに対しての関心が高まってきて、原因のわからない様々な症状が実は食べているものが原因であるということが分かって来ています。そして、その原因食材を食事制限することで、症状が改善することから「小麦を食べてはいけない」とか「乳製品は食べてはいけない」という情報が氾濫しています。
それに対して警鐘を鳴らすという意味で、「小麦アレルギーも、小麦制限をすることが根本的治療ではありません」と言って来たのですが、それがいつの間にか「小麦アレルギーがあっても、制限しなくて食べても問題ない」というふうに誤解されることがあると気付かされたのです。
私が言いたいことは、当然小麦アレルギーがある人が、いきなり小麦を食べてくださいということではありません。
小麦アレルギーの原因が、もし小麦自体にあるのであれば、もっと多くの人が小麦を食べるとアレルギー症状が出るはずです。しかし、現実は9割以上(9.9割以上と言ってもいいかもしれません)の人が何の問題もなく、小麦を食べているのです。つまり、100人のうち1人か2人かの人が、小麦が原因でアレルギー症状が出るからといって、小麦を悪者扱いするのは真実でしょうか?
むしろ、本当の原因は小麦自体ではなく、その小麦に対して過剰な反応をする腸内環境自体ではないでしょうか、というのが私の言いたいことです。そして、その腸内環境を整えることで、小麦を食べてもアレルギー症状をなくしていく方がより根本的な治療ではないでしょうかと言いたいのです。
実際、当院で腸内環境を整える治療を行うことで、小麦に限らず様々な食物アレルギーの症状が改善し、何を食べても症状が出なくなった方は、数え切れないくらいいらっしゃいます。ただ、腸内環境がきっちりと整うまでは、症状が出る間はある程度の食物制限はしないといけません。
この、「腸内環境が整うまでは制限が必要」という大切な条件が、動画を見てくださる方に十分に伝わっていなかったのかと反省した次第です。
私は診察の時には、「最終的には、何を食べてもアレルギー症状が出ない体に整えていきましょう。それまでの治療途中ではある程度の制限は必要な場合がありますよ。」とお伝えしています。
その点をもう一度きっちりと、誤解のないように伝えたくて、今日の記事を書かせていただきました。
執筆者プロフィール

医療法人全人会理事長、総合内科専門医、医学博士。京都大学医学部卒業。天理よろづ相談所病院、京都大学附属病院消化器内科勤務を経て、2013年大阪市北区中津にて小西統合医療内科を開院。2018年9月より医療法人全人会を設立。